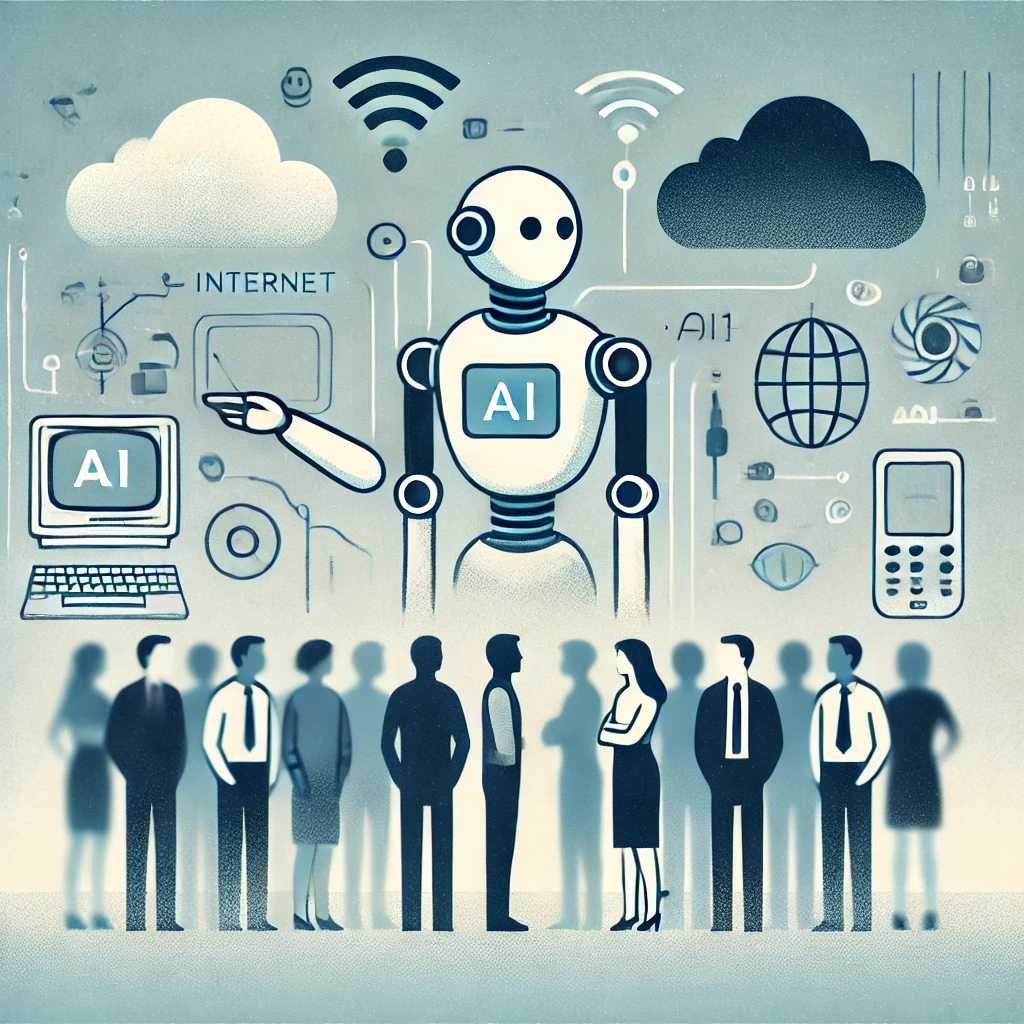
09 [2024年1月] デジャヴュの正体 〜 過去の経験が照らす、AI普及への道
前回は、AIの可能性を周囲に伝えようとする中で感じた、熱狂と現実のギャップ、そして、その「もどかしさ」 についてお話ししました。今回は、その「もどかしさ」の正体に気づき、過去の経験から得た、AI普及へのヒントについて書きたいと思います。
もどかしさの正体 〜 理解と共感の欠如
AIの有用性を周囲に理解してもらえない。その状況に、私は日々もどかしさを感じていました。「なぜ、こんなに便利なツールなのに、みんな使おうとしないのだろう?」そんな疑問を抱えながら、私は、ギャップの原因を考え続けました。
そして、ある時、ふと気づいたのです。私自身が、AIの凄さを一方的に語るだけで、周囲の理解や共感を得るための努力を怠っていたのではないか? と。
私は、AIの可能性に興奮するあまり、その技術的な側面や、先進性ばかりを強調していました。しかし、多くの人にとって、AIは未知の存在であり、漠然とした不安や抵抗感を抱かせるものでもあったのです。
「この感覚、前にも…」 〜 過去の記憶が蘇る
そんな気づきを得た時、私は、このもどかしさの感覚を、以前にも経験したことがあることを思い出しました。
インターネットが普及し始めた頃、その可能性を周囲に熱く語っても、なかなか理解してもらえなかったあの頃。
クラウドサービスの便利さを力説しても、「セキュリティが心配」と敬遠されたあの頃。
iPhoneが登場した時、「こんなにすごいデバイスは、きっと世界を変える!」と興奮しても、「日本では流行らないよ」と冷ややかに返されたあの頃。
これらの記憶が、走馬灯のように蘇ってきました。そして、AIを前にした今の状況が、それらの過去の出来事と、見事に重なって見えたのです。
デジャヴュの正体 〜 新しいテクノロジーの普及曲線
過去を振り返ってみれば、インターネットも、クラウドも、iPhoneも、登場した当初は、多くの人にとって未知の存在であり、懐疑的に見られていました。 しかし、それらのテクノロジーは、今では私たちの生活に欠かせないものとなっています。
この経験から、私は、新しいテクノロジーが普及する過程には、一定のパターンがあるのではないかと考えました。最初は、一部のアーリーアダプターがその可能性に気づき、熱狂する。しかし、多くの人々は、その価値を理解できず、懐疑的、あるいは無関心な態度を取る。そして、時間の経過とともに、そのテクノロジーが社会に浸透し、徐々に人々の生活を変えていく。
AI普及へのヒント 〜 理解と共感を生む「伝え方」
今、私たちは、AIという新しいテクノロジーの黎明期に立ち会っています。そして、かつてのインターネットやクラウド、iPhoneのように、AIもまた、私たちの社会を大きく変える可能性を秘めています。
だからこそ、今はまだ、多くの人に理解されなくても、それは当然のことなのかもしれません。しかし、この「デジャヴュ」を確信に変え、AIの可能性を信じ、伝え続けることが重要なのではないか。
そして、そのためには、一方的にAIの凄さを語るのではなく、相手の立場に立ち、理解と共感を生むような「伝え方」を工夫する必要があると、私は考えるようになりました。
