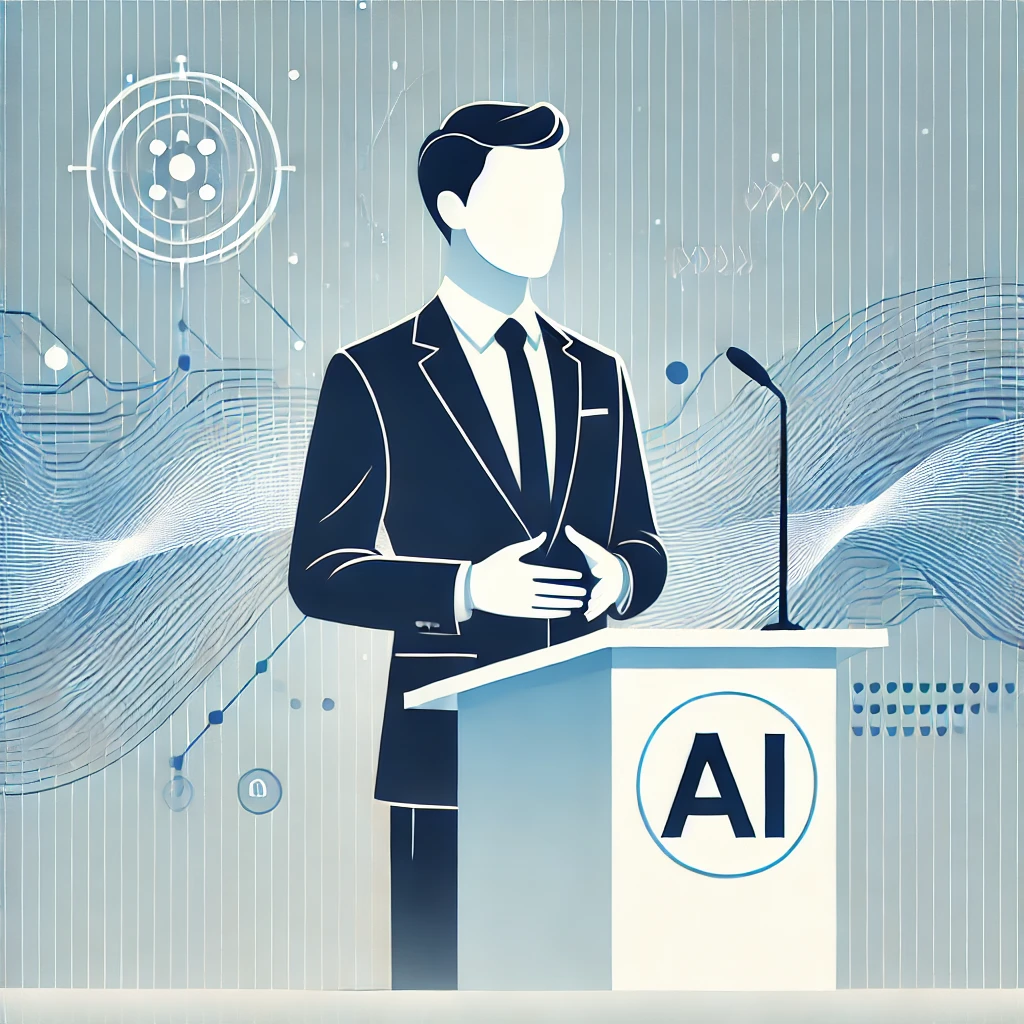
17[2024年9月]AI活用を外に広げる 〜 経営層との対話で感じた、AIの可能性
前回は、自分自身のAI活用をさらに深めるために作成した「AI活用のための手引き」についてお話ししました。この「手引き」は、私のAI活用を次のステージへと導いてくれました。そして私は、この「手引き」を携え、再び外の世界へと目を向けることにしました。ただし、会社内では、AIについて話すことはもうありません。約1年間の「潜伏期間」を経て、AIに関する知識も、活用スキルも、格段に向上したと自負しています。しかし、社内には、それを披露する場も、理解してくれる人も、ほとんどいなかったからです。
業務外での出会い 〜 中小企業経営者との会話
私の仕事は、中小企業の経営者と接する機会が多くありました。 業務の相談を受けたり、経営課題について意見交換をしたりする中で、AIの話題が出ることも、徐々に増えてきました。
ある日、私は、ある経営者団体に所属するA社長と、懇親会でお話しする機会がありました。A社長は、地元の経済界で長年活躍されている、経験豊富な経営者です。
「最近は、AIという言葉をよく聞くようになりましたね」とA社長。「しかし、正直なところ、自分の会社でどう使えばいいのか、よく分からないんですよ。」
私は、AI活用の可能性について、A社長に熱心に説明しました。しかし、以前の私のように、一方的にAIの凄さを語るようなことはしません。A社長の事業内容や、経営課題を丁寧に聞き出し、それに合わせて、AIの具体的な活用方法を提案するように心がけました。
役員就任スピーチをAIで作成 〜 驚きと可能性の発見
そんな中、A社長は、近々、その経営者団体の役員に就任することが決まっており、就任スピーチの準備に頭を悩ませていることを、打ち明けてくれました。
「就任スピーチか…。何を話せばいいのやら…」と、困り果てた様子のA社長。私は、「それなら、AIでスピーチを作ってみませんか?」 と、冗談半分で提案してみました。
最初は、A社長も「AIでスピーチを作るなんて、そんなことができるのか?」と半信半疑でした。しかし、私は、その場で、ノートパソコンを取り出し、AIを使ったスピーチ作成の実演を始めました。
まず、Gensparkを使って、その経営者団体の概要や、最近の活動内容、地域経済の動向などを、素早く調査しました。そして、それらの情報をPerplexityにインプットし、「この団体の役員就任スピーチを考えてください」と指示を出しました。
すると、わずか数分で、Perplexityは、A社長の経歴や、経営理念、そして団体の活動方針などを踏まえた、見事な就任スピーチを生成したのです。
経営者の視点、銀行員の視点 〜 AI活用への期待
「これはすごい…! まるで、自分が書いたみたいだ…!」
A社長は、Perplexityが生成したスピーチを見て、驚きの表情を隠せませんでした。そして、「AIを使えば、こんなに簡単に、質の高いスピーチが作れるのか…」 と、感嘆の声を漏らしました。
さらに、その様子を隣で見ていた、同席していた銀行の担当者Bさんも、「これは、自分の業務にも活用できるかもしれない…」 と、AI活用に強い関心を示してくれました。Bさんは、普段から、企業の決算書を分析したり、融資の提案資料を作成したりする業務に携わっており、AIを使った情報収集や資料作成の効率化に、大きな可能性を感じたようです。
「これまでの調べる時間は何だったのか、資料作成に費やしていた時間は何だったのか」と、Bさんも、驚きを隠せない様子でした。
経営層とAIの親和性 〜 決断と実行のスピード
この経験を通じて、私は、経営者や経営層は、AIと非常に親和性が高いと、改めて感じました。なぜなら、彼らは、常に、事業の成長や、業務の効率化について考えており、新しいテクノロジーに対する感度も高いからです。
そして、AIの可能性を理解した時の、決断と実行のスピードが、一般社員とは段違いに速いのです。A社長は、この一件以来、積極的にAI活用を推進するようになり、自社の業務にAIを導入するためのプロジェクトを立ち上げました。
AIの活用は、企業にとって、競争優位を築くための重要な鍵となります。そして、その鍵を握っているのは、経営層なのです。私は、経営層へのAI活用提案を、より積極的に行っていく必要があると、強く感じました。
