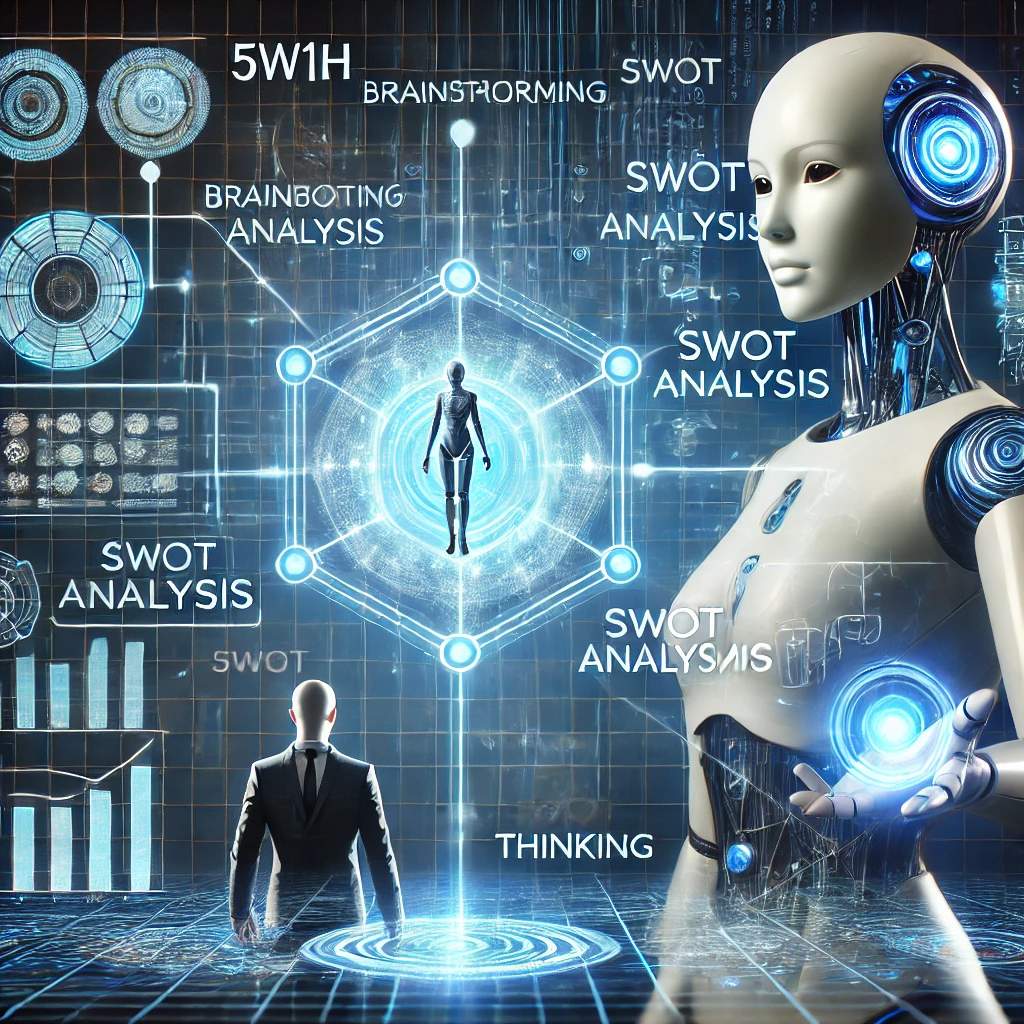
16 [2024年9月]AI活用、次のステージへ 〜 言語化と思考のフレームワークで、AIを真のパートナーに
前回は、AIを使わない人、使えない人の特徴を分析し、その原因として「人に質問したり指示したりすることが苦手」という点に焦点を当て、言語化やアウトプットの重要性について論じました。AIを使いこなすための「プロンプト」は、実は、現実世界におけるコミュニケーション能力と密接に関連しているのではないか、という仮説を提示しました。今回は、この仮説に基づき、私が作成した「AI活用のための手引き」 についてお話しします。
AIを使いこなすための「壁」
前回の考察から、私は、AIを使いこなすための「壁」は、技術的な問題よりも、むしろ思考や言語化といった、より根本的な部分にあるのではないかと考えました。
そこで、AI活用に躓いている人でも実践できる、思考を整理し、言語化を促進するための「フレームワーク」 をまとめた、「AI活用のための手引き」 を作成することにしました。
「手引き」作成のプロセス 〜 フレームワークの洗い出し
まず、私は、自分が普段どのように考え、どのようにAIに指示を出しているのかを、改めて振り返ってみました。そして、そのプロセスを、いくつかの「フレームワーク」として抽出しました。
具体的には、以下のようなフレームワークを洗い出しました。
- 情報収集のためのフレームワーク: 5W1H、ペルソナ分析 など
- アイデア出しのためのフレームワーク: ブレインストーミング、マンダラート、SCAMPER法 など
- 思考を整理するためのフレームワーク: ロジックツリー、SWOT分析、MECE など
- 課題解決のためのフレームワーク: DMAIC、PDCAサイクル、根本原因分析 など
これらのフレームワークは、AI活用に限らず、ビジネス全般で役立つ、汎用的な思考の型です。
「手引き」の内容 〜 実践的な解説とAI活用例
次に、私は、洗い出したフレームワークについて、一つ一つ丁寧に解説を加えました。そして、それぞれのフレームワークを、どのようにAI活用に応用できるのか、具体的な例を挙げて説明しました。
例えば、「情報収集のためのフレームワーク」の「5W1H」であれば、
- What(何を): 何について調べたいのか?
- Why(なぜ): なぜそれを調べる必要があるのか?
- Who(誰が): 誰に関する情報が必要なのか?
- When(いつ): いつ時点の情報が必要なのか?
- Where(どこで): どの地域、どの国の情報が必要なのか?
- How(どのように): どのように情報を収集するのか?
といった具合に、質問を細分化します。そして、これらの質問をプロンプトとしてChatGPTに入力することで、より具体的で、精度の高い情報を得ることができる、といった具合です。
「手引き」完成、そして新たな気づき
こうして、私は、AIを使いこなすための「思考」と「言語化」のフレームワークをまとめた、「AI活用のための手引き」を完成させました。
この「手引き」を作成する過程で、私自身、自分の思考プロセスや、AIへの指示の出し方について、改めて見直すことができました。そして、フレームワークを意識することで、より効率的に、より質の高いアウトプットを、AIから引き出せるようになったのです。
「手引き」がもたらした、自身のAI活用の深化
「手引き」は、私自身のAI活用を、さらに深化させることに大きく寄与しました。それまで、なんとなく使っていたAIツールに対しても、「手引き」にあるフレームワークを意識することで、より明確な目的を持って、より効果的に活用できるようになったのです。
例えば、複雑な問題に対しても、フレームワークを使って問題を分解し、一つずつ丁寧に検討していくことで、AIから、より深い洞察を得られるようになりました。
この「手引き」は、AI活用の「羅針盤」 のようなものです。これがあれば、AIという大海原で迷子になることなく、目的地に向かって航海することができるのです。そして、この「羅針盤」を手に、私は、AI活用のさらなる可能性を追求していくことになります。
